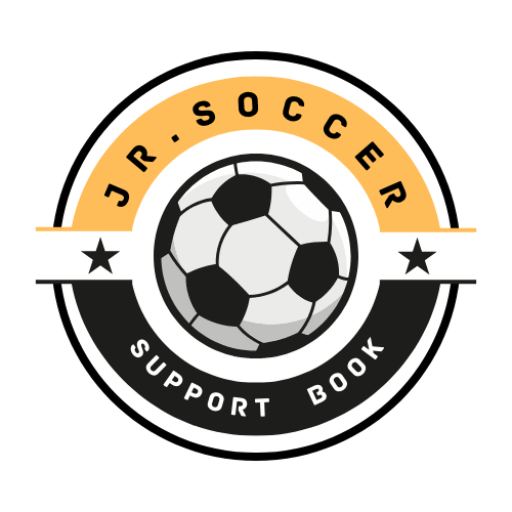低学年のサッカー指導で大切なポイント
こんにちは。三兄弟パパコーチです。
小学生低学年、とくに1年生・2年生の子どもたちは集中力が長く続きません。
一つの練習メニューでも途中で飽きてしまったり、遊びに気持ちがいってしまうことは自然なことです。
そこで大切なのは 「楽しい」×「短時間」×「成功体験」 の3つを意識して子どもたちの意欲を引き出しながら、練習を進めることです。
- 楽しい:ゲーム要素や競争要素を取り入れる
- 短時間:1つの練習メニューは5分〜10分を目安に
- 成功体験:できた瞬間やテーマにチャレンジしたことをしっかり褒める
この3つのポイントを意識するだけで、低学年の子どもたちは夢中になってサッカーに取り組みます。
本日は実際に少年サッカーチームで効果のあった、または頻繁に採用している練習メニュー10選をご紹介します。
声かけの内容やルールの追加などによって、十分に実践的な練習にすることもできますので、参考にしてみてください。
小学生向けサッカー練習メニュー10選
① ドリブル鬼ごっこ
子どもたちが大好きな鬼ごっこに「ドリブル」をプラス。
全員がボールを持ってドリブルしながら逃げ、鬼は自分のボールをキープしつつ相手のボールをタッチします。
- ポイント:自然と顔を上げながらドリブルする力がつく
- 工夫:制限エリアの広さを調整すればスピード感もコントロールできる
油断すると「他の子のボールを制限エリアから蹴りだすゲーム」になりがちで、「ボールを奪う=マイボールにする」ことと矛盾してしまいます。
2~3回ゲームを進めながら、追加ルールとして「足の裏で引いたり身体を入れたりして、自分の足元にボールを置けたら蹴りだそう」など、ボールを奪う意識を高めてあげると一気に実践的になります。
② ボール取りゲーム(1対1)
子ども同士で1対1を行い、相手のボールを奪い合いながらドリブルでゴールを目指すゲーム。
「攻撃ではボールを守りながら運ぶ」「守備では相手の動きを読む」ことが自然に学べます。
- ポイント:ゴールの数や位置によって、スピードの強弱や方向転換(ターン、キャンセル)を多く発生できる
- 工夫:1回の時間を30秒程度にすると集中力が続きやすく、色々な相手とローテーションしやすい
低学年のうちから運ぶドリブル、はがすドリブル、ボールを守るドリブルなどにある程度自信を持てないと、以降のカテゴリで効果的にドリブルを選択できない、パス最優先の選手になってしまいます。
必ずしも突破でなくても、ボールを持つ=時間を作るプレーに活きますので、ボール保持をあきらめないことを意識させます。
③ コーンジグザグドリブル
コーンを4〜8個並べてジグザグにドリブル。基本のボールコントロール練習です。
- ポイント:速さよりも正確さやボールの置き所を重視する
- 工夫:最後に「誰が一番きれいにできたか」をみんなで評価して盛り上げる
はじめはとにかくボールタッチと身体操作に注目して声かけします。
「アウトサイド(小指)だけで」「大きなダブルタッチで」などタッチ箇所を変えるだけでも様々な身体操作を学べます。
慣れてきたら少しずつヘッドアップ、ルックアップを促すなど、実践的な発展が可能です。
④ パス&ムーブゲーム
パスを出したら自分も走って新しい位置に移動する練習。
子どもたちはついボールを見て止まってしまいがちですが、この練習で「動きながらパスをつなぐ」感覚を覚えられます。
- ポイント:最初は2人組、その後3〜4人に増やす
- 工夫:「パスを出したらゴールや次のスペースを目指す」と意識させる
「5秒以内に移動しよう」「前の人がいなくなったスペースを見つけて移動しよう」など時間やスペースを意識させることで、目的がパスを出すことで終わらずにプレーの連続性を促しながら、わいわい盛り上がれます。
⑤ シュートチャレンジ(的当て形式)
ゴールの端にコーンやマーカーを置いて「的」にし、シュートで当てたら得点。
ただのシュート練習よりも夢中になります。
- ポイント:強いシュートよりも狙って蹴る意識
- 工夫:コーチが「実況風」に盛り上げるとさらに楽しい
とにかく気持ちよく楽しませてシュートを打たせます。
「的」を置くことで自然とシュートの前にゴールを見ることも癖づきますし、より集中できます。
シュート(キック)の得意不得意を指摘し過ぎずに、シュート練習を楽しいものにしてあげます。
⑥ 3対1 ボール回し(鳥かご)
3人でパスをつなぎ、1人のディフェンダーがボールを奪いに行く練習。
低学年でもルールを簡単にすればすぐ理解できます。
- ポイント:パスを受けたらすぐに次の動作へ
- 工夫:制限時間を設けて「〇秒守りきれたら勝ち」にすると燃える
パスライン、サポート、プレー選択肢、プレー準備を作るための導入でもあり王道的メニューです。
低学年は、目線はもちろん、身体の向きもボールだけになりがちです。
「遠いほうの足でコントロールしてみよう」などオープンな身体の向きを作るメリットも伝えながら、ボールと自分だけではない、味方、そして相手との関係を意識させることにもとても効果的です。
⑦ カラーコーン反応ドリブル
何色かのカラーコーンを複数並べ、コーチが次々と色指定する声かけに応じてドリブルで目指しコーンをタッチする練習。
自在にドリブルできる身体操作やボールタッチを学べます。
- ポイント:反応スピードと切り返しを促す
- 工夫:声だけでなく、コーンと同色マーカーを上に挙げるなどで「見る」要素もプラス
⑧ リフティングチャレンジ(時間制)
「1分間で何回できるか」に挑戦。
最初は3回でもいいので「昨日より増えた!」を感じられるのが大切です。
- ポイント:続けるモチベーションを与える
- 工夫:回数が増やせた子をみんなで称えるようにすると全員のやる気UP
リフティング初心者はワンバウンドリフティングからで全く問題ありません。
一方、上級者にはインサイド、アウトサイドなどのタッチ箇所指定や蹴り上げるボールの高さ指定などで難易度調整が可能なので、一人ひとりに合ったハードルの設定ができます。
⑨ ミニゲーム(3対3)
少人数で試合形式を行うと、全員がボールに触れる機会が増えます。
試合感覚を早く身につけるのに効果的。
- ポイント:ポジションを決めずに自由にプレーさせる
- 工夫:得点したら「チーム全員でハイタッチ」を徹底すると雰囲気が良くなる
得点する、シュートを打つ、ドリブルで運ぶ選手は分かりやすく褒めやすいですが、ボールを奪いに行く、ゴールを守ることにも積極的になれるよう声かけします。
コーチがフリーマンとして参加すれば、ボールに触れられない子が出ないようにしたり、ゲーム強度もコントロールできます。
ゲーム形式なので、サッカーのルールも一緒に教えることができます。
⑩ 親子対決ゲーム
最後は親も一緒に参加してのゲーム。
子どもたちは「親に勝ちたい!」という気持ちで必死になり、盛り上がります。
- ポイント:親御さんも本気すぎず、ちょっと負けてあげるのがコツ
- 工夫:親子で一緒に笑顔になれるのでチームの雰囲気も良くなる
少年サッカーでは「親同士の仲の良さ、大人たちのチームワーク」は子どもたちにも大いに影響します。
サッカーを通じて、大人たちはどんな風にチームワークをしているのか、ミスした味方にどんな前向きな声かけをするのか、または味方を助けるプレーをするのか、そしてゴールや勝利を目指すのかを見せることも、とても意義があります。
低学年を飽きさせない工夫
練習メニューを工夫しても、子どもたちの集中力が続かないことはよくあります。
そこで実際に効果があった「飽きさせない工夫」をまとめます。
- 5分ごとにメニューを切り替える
→ 「次は何かな?」とワクワク感を持たせる。 - 勝敗やポイント制を取り入れる
→ 子どもは競争が大好き。「1点でも勝ったら大喜び」。 - できた瞬間・チャレンジした瞬間を大げさに褒める
→ 「今のすごい!」と大きく褒めることで自信が育つ。
この3つを意識するだけで練習の雰囲気が大きく変わります。
まとめ
今回は、小学生低学年、とくに1年生・2年生の子どもでも集中して楽しめるサッカー練習メニューを10個ご紹介しました。
- 鬼ごっこやゲーム感覚を取り入れる
- 5〜10分で切り替える
- 成功体験を積ませる
この3つを意識することで、子どもたちはサッカーを「楽しい!」と感じながら自然に上達していきます。
好きこそものの上手なれ!
ぜひ次回の練習で1つ2つ、試してみてください。
お読みいただき、ありがとうございました!